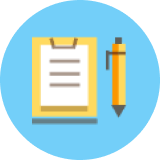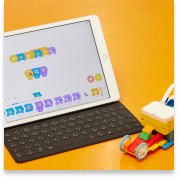公開日:2023.03.28
- プログラミング
- 専門学校
プログラミングの専門学校とはどんなところ?大学やスクールとの違いや選ぶ際のポイントを解説します

将来プログラマーやSEなどIT業界で働きたいと考えている方の中で、進学先を悩んでいる方もいるのではないでしょうか?
プログラマーやSEになるには、プログラミングの専門学校や大学に進学したり、プログラミングスクールで学んだりするなど、さまざまな選択肢があります。
その中でも、進学先で学びたいことや将来どのような仕事をしたいかといった、自分の目的に合った学校を選ぶことが大切です。
この記事では、プログラミングの専門学校とはどんなところか、プログラミングの専門学校と大学で何が違うのかを紹介します。
プログラミングの専門学校とは?どんなところ

プログラミングを学ぶ方法はいくつもありますが、専門学校で学ぶこともその一つです。
実際に進路先として専門学校を検討されている方もいるのではないでしょうか?
専門学校にはさまざまな学科があり、プログラマーやSEなど将来IT業界で働きたい方は「プログラミング学科」や「情報処理学科」などで学んでいくことになります。
専門学校とは
プログラミングの専門学校の紹介の前に、まず一般的な専門学校について見ていきましょう。
専門学校とは、専門的な学科に分かれていて実践的な職業教育がおこなわれている学校のことです。
各学科は2年制が最も多く、服飾、音楽、プログラミングといった各分野を集中的に学んでいきます。
専門学校は大学と同じ「高等教育機関」に分類されていて、入学するにも大学と同様に高校卒業相当の資格や入試に合格することが必要となります。
専門学校は平成30年度時点では全国で約2,800校存在し、約59万人の生徒が通っているというデータもあります。
専門学校の授業では特定の職業に対するスキルや経験を身につけることが重視されていて、ほかの生徒とチームを組んで作品制作や企業と連携しての実習など、就職を見据えた内容が多いことが特徴です。
プログラミングの専門学校で学ぶ内容と就職のサポート体制
プログラミングの専門学校にはさまざまな学科があり、一例としては「情報処理科」「ゲーム科」「AI(人工知能)科」「CGデザイン科」などがあります(学科の分け方や名称は各専門学校によって異なります)。
授業内容も学科によって違いますが、最初に基礎的なことを学び、段々とチームでの作品制作や企業での実習など本格的な内容に移っていき、最後は卒業制作をおこなうという流れが多くなっています。
実習に重きを置いていたり、途中で資格取得目指すなど学校や学科ごとに特色があるので、パンフレットなどであらかじめ確認しておくといいでしょう。
一例として、東京工科大学を併設校にもつ日本工学院の「情報処理科」の授業内容を簡単に紹介します。
アプリやシステム開発を目指す学科ですが、1年次では「Web開発基礎」や「データベース基礎」など基礎的なことに時間を多く割いているのがわかります。
基礎的なことを学んだ後2年次からはチームでのアプリ開発など実践的な内容に移っていくことが多いです。
ほかにも「プレゼンテーション」「ビジネススキル」「キャリアデザイン」といったプログラミングだけでなく就職に関する授業もあります。
このように、基礎から実践、それに就職やキャリアに関わることも教えてもらえるため、未経験からその分野で働くためのスキルを身につけていくことができるといえるでしょう。

専門学校の学科は2年が最も多いですが、3年、4年と長期間に渡るものもあります。より時間をかけてしっかりと学んでいきたいという方は検討してみるといいでしょう。
また、専門学校では就職のサポートをおこなっている場合も多くあります。
先ほど紹介した日本工学院では専門の「キャリアサポートセンター」を設置していて、プロのキャリアコンサルタントによるカウンセリングや、合同説明会・セミナーの開催など多くのサポートをおこなっています。
プログラミングの専門学校に進学すると
具体的に、進路のイメージを2つご紹介します。
ゲーム開発に関わりたい
将来ゲームの開発に関わりたいと思っている人が、ゲームプログラマーの養成を掲げる専門学校に入学したとします。
まずはじめにゲーム開発の基礎を学び、CGやデザインの授業を履修し、次第にオリジナルゲームが開発できるようなハイレベルなプログラミングスキルを身につけていくでしょう。
現役のプログラマーが講師を勤めている専門学校などでは、有名なゲーム会社と連携した講義を受けられることもあります。
卒業後の進路には、ゲーム会社を選ぶことが多いでしょう。
SEとして働きたい、そのための資格を取得したい
将来はプログラマーやシステムエンジニアとして活躍したいと思っている人が、IT全般を学ぶために、プログラミングに関する国家試験の合格を目指す専門学校に入学したとします。
まずはじめにIT(情報技術)に関する知識や、コンピューターの仕組みを学びます。
その後、複数のプログラミング言語やシステム開発に必要となる技術の習得を実践形式で取り組みます。
ITに関連する基本的な知識・技術を身につけていることの証明になる資格「基本情報技術者試験」などにも取り組みます。
資格試験のほかにも、年次が上がってからプロジェクトマネジメントの業務ノウハウを学んだり、グループワークを中心にシステムエンジニアとしての実力を伸ばす実習を積んだりします。
卒業後の進路は、IT関連の企業や、業界は問わずメーカー企業のIT部門に進むことが多いでしょう。
専門学校と大学のプログラミングの違いは?

プログラミングを学ぶにあたって進学先の選択肢として、専門学校と大学で迷う方もいるでしょう。
専門学校には専門学校の良さ、大学には大学の良さがあります。
学びたいことや将来やりたいことなど、個人の希望によって大学と専門学校のどちらの選択がよいかは変わってくるので、それぞれの違いを比較してみましょう。

大学で学ぶプログラミングとは
広く学んだものの中から自分で専門領域を選択したい方や、卒業後はプログラマー以外の道も検討している方には、大学で学ぶ環境が合っているかもしれません。
専攻分野以外も広く学べ、豊富な知識を修得できる
大学では、情報の専攻分野だけでなく「一般教養」の講義もあります。
専攻分野の講義では、実践的なプログラミングスキルというよりも、コンピューターの仕組みの理解やインターネットやシステム・プログラムの中身などにまつわる知識を、学問として習得できます。
どちらかというとコンピュータについて幅広く学んでいきたい、という方に向いているといえるでしょう。
学士の取得で、卒業後の進路の幅が広がる
就職活動の際、総合職の採用試験などでは、大学卒業を応募条件としている場合があります。
大学でプログラミングに関する知識を身につけつつ大卒を得ておくことで、将来プログラマー以外の職業に興味が出てきた場合にも、幅広く挑戦することが可能です。
専門学校で学ぶプログラミングとは
専門学校は学びたい分野(ゲーム開発やAI系など)が決まっている方や、実際にプログラムを書きながら実践的にプログラミングを学びたい方に向いているといえるでしょう。
短期集中で、実践的に学ぶ
専門学校の修学期間は2年が最も多くなっており、短期間で実践的に就職までのスキルを身につけることを目指しています。
授業内容もゲーム制作コースならチームを組んでゲーム制作をおこなったり、実際のゲーム会社で実習をおこなうなど実践的な内容が多いことも特徴です。
就職の斡旋や、内定までのサポート
専門学校ならではの業界とのコネクションにより、就職先の斡旋も手厚いのが専門学校の特徴です。
IT業界全体で人材不足ということもあり、就職率100%をうたっている専門学校も少なくありません。
卒業生を多く輩出している専門学校では、内定までのサポートだけでなく、就職希望先の企業担当者に自分の作品をアピールできるチャンスがあることもあります。
専門学校とプログラミングスクールの違いは?

専門学校のほかにプログラミングを学ぶ場として「プログラミングスクール」もあります。
プログラミングスクールは民間の企業などが運営しており、専門学校や大学とは違い基本的に入学の資格や試験などはなく、誰でも通うことができます。
プログラミングスクールでは、「Python(パイソン)」や「JavaScript(ジャバスクリプト)」などプログラミング言語ごとに細かくコースが分かれており、一つのコースを3ヶ月~12ヶ月など短い期間で集中的に学んでいきます。
一つのプログラミング言語など限定された範囲を集中的に学んでいくため、コース単位では専門学校より短い期間で学べ、比較的費用も安い傾向があります。
プログラミングスクールでは実際の教室へ通うこともありますが、オンラインのみで授業が完結するスクールや授業が録画されており自由な時間に学ぶことができるスクールもあるなど、社会人にも通いやすくなっていることも特徴的です。
個人で進めていくスタイルが多く、一部に「チーム開発コース」などがある場合もありますが、基本的にはほかの受講生と一緒に何かを制作することは多くありません。
またプログラミングスクールも、就職や転職のサポートとして、キャリアカウンセリングや求人紹介をおこなっている場合があります。
コース内容や料金、授業の形式などはプログラミングスクールによって大きく異なります。自分の目的と合っているか事前にホームページなどで確認することや、スクールの無料体験などを活用して選んでいくことが大事です。
プログラミングの専門学校を選ぶ際のポイントとは?

プログラミングを学ぶ環境は多くありますが、専門学校を選ぶ際のポイントについて解説します。
カリキュラムの中身、学ぶ内容
自分がどのような専門性を身につけていきたいか、その方向性に合った内容を学習できるのか、しっかり見極めましょう。
座学の時間、チーム開発などの実習時間などは、チェックしておきたいポイントです。
環境など、大事にしたい条件を満たしているか
専門学校は通学する場合が多いので、アクセスや、学費面などの条件を満たせるかも検討しましょう。
学校によっては、プロの開発環境と同じハイスペックなPCやVR機器、プログラミング用ロボット教材などの設備を取り入れているところもあります。また、学校の規模や学科の数なども異なります。
専門学校ではオープンキャンパスが開催されています。自分に合う環境を探すには、一度訪れてみることも大事です。
また、就職したい企業がある場合は、卒業生に就職実績があるかどうかも確認しておくといいでしょう。
プログラミングの専門学校についてまとめ

プログラマーになるには、さまざまな方法があります。
プログラミングを学ぶ環境の違いや、進学先を選ぶポイントを紹介しましたが、専門学校と大学のどちらへ進学するか、具体的にどの学校にしようか悩むこともあるでしょう。
そのようなときは、専門学校の体験入学や大学のオープンキャンパスに行って、実際に雰囲気を体験してみてはいかがでしょうか。
もしまだやりたいことが決まっていない場合には、先にプログラミング学習をはじめてみることで、チャレンジしてみたい方向性が見つかるかもしれません。
高校生までのプログラミングならLITALICOワンダー

LITALICOワンダーは、高校3年生までのプログラミング教室を運営しています。
決められたカリキュラムをこなすような授業ではなく、一人ひとりの「〇〇をつくりたい!」という気持ちを重視し、オーダーメイドのカリキュラムで個別の授業をしています。
例えばRPGゲームが好きな子どもの場合、ゲームプログラミングの基礎を学んだ後、オリジナルストーリーやキャラクターづくりといった演出にこだわることで、さらに学びを深めていくことができます。
プログラミングに興味がある方は、ぜひ一度お気軽に無料体験にお越しください。