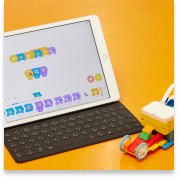最終更新日:2023.02.11
公開日:2019.04.18
- プログラミング教育必修化
プログラミングは何歳からできる?年齢別におすすめの教材も紹介します

子どもの習い事として最近特によく注目されているプログラミング教室。
身近にたくさんのプログラミング教室がオープンしているかもしれません。
習い事をスタートするには、「適齢期」(=何歳から始めれば最も効果的か?)を気にされる保護者の方もいらっしゃることと思います。
そこで、今回はプログラミング学習を何歳から始めるべきかについて、教材や教室の対象年齢なども踏まえながら紹介いたします。
\プログラミング教室の授業を無料で体験!/
プログラミングは何歳からできる?

もし、プログラミングを学びたいと思ったら何歳くらいからスタートできるのでしょうか?
結論を言えば、プログラミング学習のツールが充実する4歳頃から楽しみながらプログラミング学習をスタートできます。
幼児におすすめのプログラミング教材

低年齢からスタートできるプログラミング学習ツールには、以下のようなものがあります。
- Viscuit(ビスケット):4歳~
- Lightbot(ライトボット):4歳~
- Scratch Jr(スクラッチジュニア):5歳~
これらのプログラミング学習ツールは、PCやタブレットの画面の絵やキャラクターを指示・命令によって動かしたり、与えられた課題を解いたりすることができるツールです。
視覚的・直感的にゲーム感覚でプログラミングの考え方を学ぶことができます。
アプリやブラウザで楽しめるツールで、無料で始めることができます。
プログラミング学習を見据えた幼児期の遊びはブロック遊びもおすすめ!
もし、将来プログラミング学習を始めることを見据えた遊び方を探されている場合、レゴ®などのブロック遊びがおすすめです。
元々、レゴ®ブロックは知育玩具としての評判も高く、2018年にレゴジャパン株式会社が東京6大学出身の600名を対象に行ったアンケート調査によると、東京大学出身者の68%が幼少期にレゴ®ブロックで遊んでいた、というデータもあります。
プログラミング教室で実施しているロボットプログラミングでも、まずブロックの組み立てをおこなってから最後にプログラミングをするという流れの授業がほとんどなので、ブロックの組み立てに慣れておくと、ロボットプログラミングもスムーズに取り組めるでしょう。
また、頭の中で完成イメージを描いて、試行錯誤をしながら思い描いた形を作り上げていく工程は、プログラミングにも通じる部分があります。
インターネット環境やコンピュータも不要なので、ぜひ親子でブロック遊びを一緒に楽しんでみてください。
小学生におすすめのプログラミング教材

小学生になると使用できる教材のバリエーションはさらに広がります。
- Scratch(スクラッチ):8歳~
- レゴ®エデュケーションWeDo2.0:7歳〜
対象年齢はあくまで目安ですので、子どもが興味を持てば特に対象年齢にこだわる必要はありません。
例えば5歳になる前にScratch Jrを始めても良いですし、対象年齢が8歳~となっているScratchを早くスタートするのも良いでしょう。
重要なことは、子どもたちが楽しみながら「プログラミング的思考」を身につけられることです。
最初から正解にたどり着くのは容易ではなく、失敗と工夫を繰り返すことがプログラミングの醍醐味です。
そしてその過程で、子どもたちは主体性や論理的思考力を伸ばしていきます。
教材を使用する際のポイントとして、手が小さく細かな動きが難しい幼児にはタブレット端末がおすすめです。
レゴ®ブロックなどを用いてブロックの組み立てに慣れ親しんでおくことも良いでしょう。
また、PCの操作に不慣れな小学生はマウス操作のみでおこなえるプログラミング教材からスタートするとスムーズです。
子どものプログラミングが大切な理由

そもそも、なぜ子どものプログラミングは大切なのでしょうか。
プログラミング教育の目的
プログラミングの技術を使う仕事としては、真っ先にプログラマーを思い浮かべる方が多いと思います。
しかし、多くの子ども向けプログラミング教室や、2020年から新学習指導要領に盛り込まれた小学校でのプログラミング教育では、将来のプログラマーを育成しようとしているわけではありません。
プログラミング教育は、「現代の読み・書き・そろばん」ともいわれており、グローバル化・IT化という激動の時代で活躍するために必要なスキルを身につけるのに適しているといわれているのです。
2020年度から全面実施された新学習指導要領、文部科学省の「小学校学習指導要領総則」においても、以下のように明記されています。
子供たちが将来どのような職業に就くとしても時代を越えて普遍的に求められる「プログラミング的思考」を育むため,小学校においては,児童がプログラミングを体験しながら,コンピュータに意図した処理をおこなわせるために必要な論理的思考力を身に付けるための学習活動を計画的に実施することとしている。
「小学校学習指導要領総則 」より引用
プログラミング教育で身につくスキル
具体的に、プログラミングによって身につくスキルとして下記が挙げられます。
- 論理的なものの考え方(プログラミング的思考)
- 主体性や自主性
- 創造力
これらは例えプログラマーを目指さなくとも、グローバル化やロボットやITが高度に発展したテクノロジー社会で、コンピュータを活用し生き抜いていくために不可欠な力です。
したがって、「何歳から始めれば良い?」「何歳までに始めなければ間に合わない」といった考え方ではなく、プログラミングを学ぶ目的を理解して年齢や学年、スキルなどに応じた学習をスタートすることが重要です。
アップルの創業者であるスティーブ・ジョブズ氏も、プログラミング学習の重要性について以下のように述べています。
「この国の全ての人が、プログラミングを習得する必要がある。
なぜなら、「考え方」が分かるようになるからだ。
ロースクール(法科大学院)に行くようなものだよ。
全員が弁護士になるわけではなくても、ロースクールに通うことは人生に役立つはずだ。」
プログラミング教室は何歳から通える?

プログラミングの教室に通う場合には、「5歳~」「小学校1年生~」「小学校高学年~」など、教室ごとにコース設定がされています。
具体的な対象年齢・学年については教室のホームページやパンフレットなどで確認しましょう。
対象学年・年齢はあくまで目安なので、どの年齢からスタートしても進度にはあまり影響がありません。
子どもが興味を持ったタイミングがスキルを大きく伸ばすチャンスですので、スタートするべきタイミングといえます。
それぞれの教室で体験プログラムを設けていることが多いので、まずは体験プログラムに参加してみることをおすすめします。
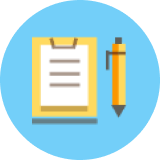
プログラミング教室は何歳まで学べる?

プログラミング教室で何歳まで学べるかについても教室によって異なります。
対象学年を小学生のみとしている教室もあれば、高校生まで通える教室もあります。
プログラミングを長く学習すればさまざまな知識やスキルを習得できるため、長く学習できる教室はとてもおすすめです。
中学生や高校生では、実用的なスマホ向けアプリを作成して一般公開したり大会(中高生向けの「アプリ甲子園」や「Unityインターハイ」など)に参加したりする生徒も数多くいます。
具体的には、高校生が開発した学生のための学習時間管理アプリやレシートの買取を1枚10円で現金化できる(企業はマーケティングに活用できる)サービスなど、高校生が開発してヒットしたアプリもあります。
ロボットプログラミングでは、プログラミングキットではなく産業用機器の工作機械の部品を用いて、高度で専門性の高いロボット工作にチャレンジする大会や、世界規模のレゴ®の大会などが行われています。
有名な大会としては、NHK主催の「全国高等専門学校ロボットコンテスト」があります。
大会のルールや協議内容は毎回変わりますが、大型のロボットを使ってボールをゴールに入れたり、指定された場所に箱を積み上げたりするなどの競技が、2チームごとの対戦形式で行われます。
出場資格が高専在学中の生徒に限られるためエントリー者は多くありませんが、地方大会と全国大会併せて15,000人以上の観客動員数があります。
また、レゴ®マインドストーム®を使用した大会「WRO」も有名です。
WRO(World Robot Olympiad)は2万2千人以上の学生が参加する世界最大規模の大会です。
メカトロニクス、通信、コンピュータ技術などの先端技術を駆使して与えられた課題をクリアするためには、高度な創造性や問題解決能力が必要とされます。
アプリ制作においてもロボット技術においても、このようなレベルになると幅広い分野の技術を組み合わせて問題を解決する力が必要となります。
ロボットの場合は工学や物理学、数学などの知識が不可欠ですし、アプリ開発の場合には英語を読む力やマーケティングに関連するスキル、デザイン設計や分析をおこなうスキルなども必要です。
プログラミング学習を通して学校では学習しないレベルの高度な知識やスキルを学び、将来の仕事などに役立つ知識を得られるのです。
プログラミングは何歳からできる?まとめ

プログラミングは、何歳からスタートしてもメリットがあります。
特に子どもが興味を持ったときには興味やスキルを伸ばす大きなチャンスです。
直接プログラミングに興味を持っていない場合でも、アプリのゲームやブロック遊びが好きな子どもの場合はプログラミング学習に夢中になることが多いので、プログラミング学習をして受動的に「遊ぶ側」から能動的な「つくる側」になれるきっかけにするのも良いのではないでしょうか?
低年齢のお子さまの場合は、まず家庭でブロック遊びを楽しんだり、お近くのプログラミング教室の無料体験授業に参加したりしてみてはいかがでしょう。
LITALICOワンダーでは、60分の無料体験授業をおこなっています。
教室は東京・神奈川・埼玉・千葉にあるほか、全国どこからでも参加できるオンライン授業もおこなっています。
お子さんがロボットやゲームが大好きであれば、ぜひ一度遊びに来てくださいね。
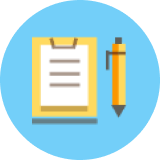
-


監修LITALICOワンダー サービス開発グループ 和田 沙央里(わだ さおり)
監修
LITALICOワンダー サービス開発グループ 和田 沙央里(わだ さおり)2014年3月株式会社LITALICOに入社。5歳〜高校生の子どもたちが通うIT×ものづくり教室「LITALICOワンダー」の立ち上げで渋谷教室の開設当初から約3年間、300名以上の通塾生徒にプログラミングの指導を続けた。2016年度は総務省「若年層に対するプログラミング教育の普及推進」事業のプロジェクト責任者を務めた。現在はカリキュラム・教材開発に携わる。大学では発達心理学・教育心理学を専攻し、卒業後は都内の大手IT企業で金融系基幹システムの開発に従事、現職に至る。
著 :『使って遊べる!Scratchおもしろプログラミングレシピ』翔泳社
監修:『スラスラ読める UnityふりがなKidsプログラミング ゲームを作りながら楽しく学ぼう! 』インプレス社
監修:『子どもから大人までスラスラ読める JavaScriptふりがなKidsプログラミング ゲームを作りながら楽しく学ぼう! 』インプレス社